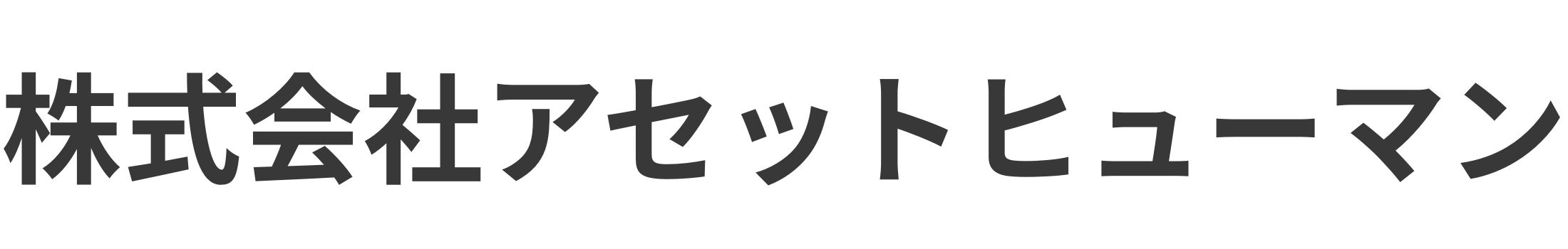サービス案内
株式会社アセットヒューマン
業務の煩雑さ、属人化、人手不足、非効率な手作業……
日々の業務運営において、こうした課題を感じていても、改善の一歩を踏み出す時間やノウハウが足りない。そんな企業様のために、株式会社アセットヒューマンは“実務に効く外部支援体制”をご提供しています。
当社では、「リモートアシスタントサービス」と「DX・業務自動化支援」という2つの柱を通じて、クライアント企業のバックオフィス機能を支え、再現性と継続性を兼ね備えた業務体制の構築を支援しています。
リモートアシスタントサービス
経理・人事・総務など、日々発生するバックオフィス業務。
「引き継ぎができない」「特定の人にしかできない」「急な欠員に対応できない」といったお悩みはありませんか?
アセットヒューマンのリモートアシスタントサービスは、複数名の専門チーム体制により、こうした属人化のリスクを排除し、継続可能な業務の仕組み化を支援します。
社内に専任の担当者がいなくても、外部チームによる安定した業務遂行が可能になる体制を、一緒につくっていきます。

経理業務
請求書の作成・送付
経費精算チェック
会計ソフトへの仕訳入力
入金管理/支払い確認

人事・労務業務
勤怠データの取りまとめ
入退社の手続き補助
給与計算サポート
雇用契約管理/書類作成

一般事務業務
メール対応
各種データの入力・集計
資料作成
スケジュール調整・管理
上記以外にも、「こういう業務をお願いしたい」といったご要望がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
業務の内容や範囲を問わず、対応可能な範囲で柔軟にお応えいたします。
アセットヒューマンでは、チーム体制での対応を基本としており、1名では難しい業務量・複雑さを含むご依頼にも柔軟に対応可能です。まずは貴社の業務や課題について、お気軽にご相談ください。
特長とメリット:
専門性の高い人材が対応
当社では、経理・人事・事務といった業務領域ごとに、実務経験の豊富な専門スタッフが在籍しており、単なるアシスタントではなく“実務のプロ”による業務支援が可能です。
各分野の業務に精通したメンバーが対応することで、クライアント様から詳細な指示がなくとも、業務内容を理解したうえで先回りした対応や提案が可能です。
「ゼロから教える必要がある」「ミスが多くて確認に時間がかかる」といった一般的な外注の不安を払拭します。

複数人による分担体制で属人化リスクを回避
通常の外注やアシスタントサービスでは、1人の担当者に依存する体制が多く、その担当者が離脱した際に業務の停止や再教育の手間が発生しやすいというリスクがあります。
当社では、業務のマニュアル化・分担体制の構築を前提に対応しているため、1名の作業者に業務が偏ることはありません。
また、複数名で情報共有・作業を進める仕組みが整っており、急な人員変更や業務の増減にも柔軟に対応できます。

マニュアル作成・業務標準化も代行
ヒアリングの段階で、クライアント様の業務内容を詳細に確認・整理し、業務フローや作業内容をマニュアルとして文書化いたします。
この工程を社内で行うには大きな労力が必要ですが、当社では初期対応の一環として標準化まで支援。
これにより、再現性のある業務体制が整い、社内での引き継ぎ・外部委託の再設計にも役立ちます。「整理されていなかった業務が見える化され、社内の改善にもつながった」とのお声を多くいただいています。

導入事例・活用シーン
- 経理担当者の退職に伴い、短期間での業務継続体制を構築したい
- スタートアップ企業で、バックオフィスの整備が手つかずの状態
- 経理や人事が他業務と兼任になっており、負荷を軽減したい
- 業務引き継ぎ時に、ドキュメント化や体制整理も併せて進めたい
- IPO準備期間に入り、体制作りをリードしてくれる人材が欲しい
- IPO準備期間中に、追加で掛かる負荷を軽減させたい
「誰がやっているかわからない業務」「その人にしかできない仕事」を残したままにすると、会社の未来は危うくなります。
アセットヒューマンのリモートアシスタントサービスなら、属人化のない再現性のある体制で、実務の土台を整えることができます。まずは、今のお困りごとをお聞かせください。
DX・業務自動化支援
「この作業、毎月同じことを手作業で繰り返している……」
「Excelの集計や転記に何時間もかかっている」
そういった状況に心当たりはありませんか?
アセットヒューマンでは、ノーコード/SaaSツールを駆使しながら、業務の一部〜全体を自動化・効率化するご提案と構築支援を行っています。
ツールに不慣れなお客様でも、業務フローの整理から伴走支援を行うことで、実務にしっかりとフィットする自動化を実現します。
主な支援内容:
複数のテクノロジーを駆使して、完全オーダーメイドで自動化します。
お客様のご希望通りのフォーマットにて、成果物を納品可能。
例:このようなパターンで「タブを開く」
- Excel、Googleスプレッドシートによる集計/自動化/関数設計
- チャットツール(Slack, Chatwork, LINE WORKS)との連携・通知自動化
- フォーム〜データベース連携の構築(例:Googleフォーム ⇔ スプレッドシート)
- 自動レポート作成(PDF・スライド生成、メール送信)
- Notionやクラウド型ツールを活用したテンプレート整備
- 簡易なRPA設計、APIの設定代行
- ツール導入後のマニュアル・ナレッジ整備
ヒアリング〜業務整理から対応可能
自動化支援といっても、最初から「この業務をこう改善したい」と明確に決まっているケースは多くありません。
アセットヒューマンでは、最初のヒアリングで業務全体を丁寧に把握し、どこがボトルネックなのか、どの作業が効率化できるのかを可視化します。
お客様と一緒に現場目線で業務を洗い出しながら、自動化・標準化・手作業の分担など、現実的なプロセスを設計いたします。
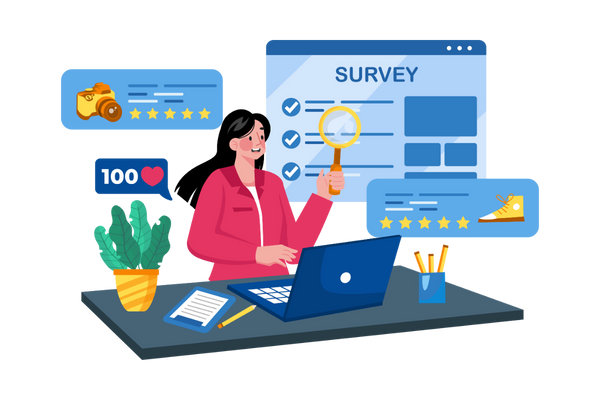
人の手による補助作業もセットで対応
自動化ツールを導入するだけでは、“使いこなす”までに時間がかかったり、想定どおりの結果が出なかったりするケースがあります。当社では、ツールだけに任せず、必要な工程には人の手を加えるハイブリッド型で対応。
たとえば、集計は自動で行い、最終レポートの仕上げは手作業でフォーマットに整えるなど、「実務で使える成果物」の納品を目指します。これにより、クライアント様側では追加作業なしで運用に移行できます。

社内にノウハウを残す運用設計
自動化ツールを「構築して終わり」にせず、納品後の運用まで見据えた設計とドキュメント化を徹底しています。
設定画面のキャプチャや操作説明のマニュアルはもちろん、「どのようなルールで動いているのか」といった業務ロジックまで見える化。
これにより、将来的な社内担当者の変更や、運用変更が発生しても、属人化せずに継続的な運用が可能になります。
必要であれば、研修会や社内展開支援にも対応いたします。

導入事例・活用シーン
- レポート・報告資料を毎月手作業で作っている
- 勤怠・売上・日報などの情報を、複数のツール間で転記している
- 入力・集計・出力のプロセスがバラバラで属人的
- エンジニアがいないため、ノーコードで運用可能な仕組みを作りたい
「自動化は難しそう」「うちの業務は特殊だから」と思っていても、現場に合わせて構築すれば、誰でも使える形で効率化は実現できます。
アセットヒューマンでは、無理なく、しかし確実に“実務を動かすDX”をサポートします。
アセットヒューマンが選ばれる理由
多くの業務委託・外注サービスでは、「依頼する内容が明確でないと進められない」「担当者が辞めるとまたゼロから説明が必要」などの課題がつきものです。
アセットヒューマンは、業務を整理し、属人化を解消し、チームで継続的に支える体制を構築できる点が、他社との大きな違いです。
一般的な外注との比較:
| 項目 | 一般的な外注 | アセットヒューマン |
|---|---|---|
| 担当体制 | 担当者1名 | 専門チームによる複数名体制 |
| 属人化リスク | 高い | マニュアル+標準化でリスク回避 |
| 業務の整理・設計 | クライアント任せ | ヒアリングから整理・提案まで対応 |
| 自動化支援の可否 | 非対応または限定的 | AI/SaaS活用で柔軟に対応 |
| 継続性・再現性 | 個人の力量に依存 | 誰でも対応可能な再現性ある体制を構築 |
| ツール導入時の費用負担 | クライアント側で契約・導入費用 | 弊社契約済ツールを活用、原則クライアント負担なし |
アセットヒューマンは「一時的な助っ人」ではなく、長期的に価値を生む業務体制を一緒に設計・構築できるパートナーです。
「業務を誰かに任せたいけれど、不安がある」
「効率化したいけど、何から始めればいいかわからない」
そんなお悩みこそ、私たちの得意分野です。
仕組み化・継続・改善を前提とした実務支援体制をお求めなら、ぜひ一度、株式会社アセットヒューマンにご相談ください。